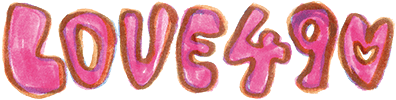新理事長、今野良ご挨拶

2024年度から、20年という歴史のある本会の理事長を務めさせていただいている今野良です。
私と子宮頸がんの出会いは、今から40年前、大学を卒業して間もなく、地方の初期研修で出会った進行期の70歳代女性でした。当時のその病院には放射線治療機器があり指導医の下、初めて放射線治療に携わり、その患者さんは途中の合併症で苦労しながらも回復し、退院することが出来ました。放射線治療の有効性を実感する経験でした。
ほどなくして、今度は極度にやせ細った60歳代の女性が運ばれてきました。意識はあり、会話はできるものの、自分では動けず食事も摂れないさまです。家族は放射線治療を希望しましたが、指導医は「体力が無く、却って命を縮めかねないから、緩和ケアを」と提案しましたが、受け入れられず、一日だけトライしてみると、もう翌日からベッドに起き上がることもできません。本人からは「立派な病院に連れてきてもらい、治療も受けさせてもらった」、これ以上は望まないという希望が伝えられ、皆が納得し支持療法だけとしましたが、3日後には息を生きとりました。
この経験が、私が産婦人科医として婦人科がんを専攻しようという動機になり、一方で、子宮頸がん検診を普及させようと思わせました。
時は流れ、いまは子宮頸がんの原因がHPV(ヒトパピローマウイルス)であることが解明され、感染防止ワクチンが開発され、検診には従来からの細胞診に替えて、高感度のHPV検査が導入されました。今のこの状況では、前述の二人のような子宮頸がん患者は存在しないのが当たり前のはずなのです。
ところが、実際には3000-4000人の患者さんが死亡し、10000人以上が新たに子宮頸がんに罹患しており、さらに増加を続けています。検診の受診率は40%程度で、HPVワクチンの接種率は定期が40%、キャッチアップが20%程度です。このままの状況では、WHOが提唱する2100年までの世界における子宮頸がん征圧(人口10万人名当たりの罹患率4人未満)に、日本は到達することができません。ほとんどの低・中所得国でも達成可能であるにも拘らず、日本だけ最悲劇国になる可能性が高いです。どうすればそこから脱却できるのでしょうが?
その解決が私たちの課題です。
さて、4月9日は「子宮頸がんを予防する日、子宮の日」として皆さんに覚えていただき、各地で子宮頸がん予防のためのイベントやキャンペーンが実施されます。なかでも、頼りがいがあるのは、細胞診断のプロである細胞検査士の皆さんのご協力である街角のキャンペーンです。本当にご苦労様です。毎年感謝しております。市民の皆様はこの機会にぜひ、子宮頸がんのことを検査士さんに尋ねてみてください。HPV検査の検診が普及すると、その後の精密検査として行われる細胞診の意義と検査士の地位は格段に向上します。
そのほかにも、事務局では3月4日の「国際HPV啓発Day」のウェビナーや、日本とアジアパシフィック地域女性の子宮頸がんへの取り組み調査と成果報告・記者会見、各自治体へのアンケート実施と後日の報告会などを予定しております。各地においては、工夫を凝らした独自の取り組みが予定されています。
実は、子宮頸がん予防のためには、生涯に「ワクチンを1回、検診を1回」するだけで大丈夫という日が近づいるのです。ぜひ、ウェビナーや街頭での出会いで話し合ってみませんか?私たちの現在と将来の健康と命を守るために!
NPO子宮頸がんを考える市民の会 理事長 今野良